2025年現在、世界中で暗号資産(仮想通貨)の投資が広がりを見せています。ブロックチェーン技術の浸透、Web3やNFTといった革新領域の成長、そして経済不安を背景に、多くの国でビットコインなどの保有率が急増しています。
とはいえ、その投資普及率は国ごとに大きな差があります。たとえば、ナイジェリアやタイでは生活インフラの一部として使われているのに対し、日本では法規制や税制の影響で出遅れている状況です。
本記事では、筆者が実際に暗号資産を活用している視点から、2025年最新の国別普及状況を比較し、その背景や今後のチャンスを深堀りしていきます。
1. 暗号資産の普及率をどう測る?信頼されるデータと分析基準
暗号資産の「普及率」とは、一般的に特定の国や地域における個人ユーザーの保有割合や取引頻度を示す指標です。
この普及率を正確に把握するには、信頼できる情報源と測定基準が欠かせません。
2025年時点で主な情報源として知られるのが、Chainalysis社の「Global Crypto Adoption Index」と、Statistaによる「Cryptocurrency ownership by country」です。
Chainalysisの指標では、次のような複数の変数を組み合わせて暗号資産の普及度をスコア化しています。
- オンチェーンでの暗号資産取引ボリューム(調整済)
- ピア・ツー・ピア(P2P)取引量
- 個人ユーザーの取引回数と規模
- 人口とGDPの影響を加味した調整係数
これにより、ただ「どれだけの金額が動いているか」ではなく、一般市民のどれくらいが実際に使っているかを明確に把握できます。
一方、Statistaでは各国のユーザー調査に基づき、全人口に対する暗号資産保有者の割合(%)を国別で示しています。
たとえば2024年末の調査では、タイ・ナイジェリア・トルコ・インドなどが上位にランクインしています(Statista, 2024年公開資料)。
このように、複数の信頼ある指標を読み解くことで、国ごとの暗号資産への関心や経済的背景が見えてきます。
次章では、実際に2025年現在で暗号資産投資が最も盛んな国TOP10をランキング形式でご紹介していきます。
本記事のデータは、Chainalysis 2024年版レポートおよびStatista掲載の2024年公開データに基づいています。
2. 【2025年最新】暗号資産投資が最も進んでいる国ランキングTOP10
2025年時点で暗号資産の普及が特に進んでいる国々は、必ずしも経済大国とは限りません。インフレ率や金融アクセス、規制緩和などが要因となり、新興国が上位を占めています。
以下は、Chainalysis「Global Crypto Adoption Index 2024」と、Statista「Cryptocurrency Ownership by Country 2024」など複数の調査を参考に作成した、普及率上位国のランキングです。
| 順位 | 国名 | 普及率(推定) | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ナイジェリア | 約45% | 法定通貨不安によりビットコインが通貨代替手段に |
| 2位 | タイ | 約44% | 若年層の投資熱と観光業での利用が進展 |
| 3位 | トルコ | 約40% | 高インフレにより資産保全手段として普及 |
| 4位 | ベトナム | 約39% | 個人投資とP2P取引が活発 |
| 5位 | アルゼンチン | 約38% | 経済危機下でUSDTなどのステーブルコインが浸透 |
| 6位 | インド | 約32% | 人口規模とデジタル教育の広がりが要因 |
| 7位 | ブラジル | 約28% | 中産階級による暗号資産保有が増加中 |
| 8位 | ウクライナ | 約26% | 軍事支援とクラウドファンディングでの利用も |
| 9位 | フィリピン | 約25% | プレイトゥアーン(P2E)系ゲームの普及 |
| 10位 | アメリカ | 約23% | 機関投資家と個人投資家が共存する先進市場 |
このランキングからは、通貨の信用不安や高インフレを抱える国ほど、暗号資産が日常の選択肢となっていることがわかります。
また、タイやフィリピンのように観光・ゲーム・若者層の要素が絡む国でも、デジタル資産の活用が自然に進んでいる傾向があります。
一方で、日本の順位はこのランキングには登場していません。その理由と課題については、次章で詳しく見ていきましょう。
参考:Chainalysis “Crypto Adoption Index 2024” / Statista “Cryptocurrency ownership by country 2024”
3. なぜ日本は遅れている?暗号資産普及率の国際比較で見える課題
暗号資産の世界的な普及が進む中で、日本の保有率は先進国の中でも決して高くありません。Statistaのデータによると、日本の暗号資産保有者は全体の約6〜8%程度にとどまり、ランキング上位の国々とは大きな差があります。
その理由を探ると、いくつかの構造的な課題が浮かび上がってきます。
① 税制の壁:利益に対する雑所得扱いが投資の妨げに
日本では、暗号資産の売買益は「雑所得」として総合課税の対象となり、最大で約55%の税率がかかる可能性があります。これにより、中長期での保有や利確のタイミングが難しく、短期売買を敬遠する個人投資家も多いです。
参考:国税庁「暗号資産に関する税務上の取扱いについて」
② 金融庁の規制体制の厳格さ
日本では金融庁が定める厳格なルールに基づき、取引所の登録要件や広告規制が設けられています。これにより、海外の取引所に比べて日本国内のプラットフォームでは取扱通貨の数やDeFi連携が限定されることが多く、ユーザーの選択肢が狭まっています。
参考:金融庁「暗号資産交換業者登録制度」
③ 金融リテラシーとメディアの影響
日本では、暗号資産が「投機的」や「危険」といったイメージで語られることが多く、健全な投資対象としての理解が進んでいません。その背景には、学校教育における金融リテラシーの低さや、過去の取引所事件(例:Mt.Gox)の影響も根強く残っています。
④ 実用シーンの少なさ
海外では日常の買い物や送金などで暗号資産を活用できる場面が増えていますが、日本ではそのようなエコシステムが整っていません。日常生活でのユースケースの乏しさも、普及を阻む一因です。
⑤ それでも広がり始めているポジティブな兆し
一方で、2024年以降は三井住友銀行・GMO・楽天など大手企業がWeb3領域への進出を進めており、徐々に投資環境の整備が進み始めています。また、NFTアートやブロックチェーンゲームを通じて、若年層の関心も高まりつつあるのは明るい材料です。
以上からわかるように、日本では制度・意識・教育など複合的な要因が絡み、暗号資産の普及が進みにくい環境にあります。しかし、改善の兆しは見え始めており、今後の政策次第で状況は大きく変わる可能性があります。
参考:国税庁・金融庁公式資料、Statista「Cryptocurrency Ownership 2024」、日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)
4. 暗号資産が進んでいる国に共通する3つの特徴
暗号資産の普及率が高い国々には、いくつかの共通した背景や社会的要因があります。ただ「先進国だから」普及するとは限らず、むしろ発展途上国や新興国の方が積極的に活用しているケースも少なくありません。
ここでは、普及国の特徴として代表的な3つのポイントを解説します。
① 高インフレ・経済不安による法定通貨への不信感
ナイジェリア、アルゼンチン、トルコといった国々では、法定通貨の価値が短期間で大きく変動することが日常的です。これらの国では、ビットコインやステーブルコイン(例:USDT、USDC)が「代替通貨」や「資産保全手段」として使われており、実用的なニーズが普及を後押ししています。
② 銀行口座を持たない層(アンバンクド)の多さ
アフリカや東南アジアでは、まだ多くの人が銀行口座を持っていません。しかし、スマートフォンとインターネットさえあれば、誰でもウォレットを持ち、暗号資産を利用できます。金融インフラの代替手段としての機能が、こうした地域での拡大を支えています。
たとえば、ケニアやベトナムでは暗号資産を活用したP2P送金や国際送金が急速に広がっています。
③ 若年層の多さとデジタル・ネイティブ文化
インドやフィリピンでは、若者が主導するデジタル経済の中で、暗号資産が投資やゲームの世界と密接にリンクしています。特にプレイ・トゥ・アーン(P2E)ゲームやNFTを通じた報酬モデルが注目を集め、暗号資産を「遊びながら学ぶ・稼ぐ」世代が台頭しています。
こうした背景が、自然な形での普及を後押ししているのです。
このように、「経済危機を乗り越える手段」「金融アクセスの代替」「若者文化との融合」が、暗号資産の受け入れを後押しする大きな要因となっています。
参考:Chainalysis “Crypto Adoption Index 2024”、World Bank “Global Findex Database”、Statista “Cryptocurrency Usage by Region”
5. 税制と規制が投資の未来を決める|各国制度比較
暗号資産の投資環境において、税制と規制のあり方は、普及率や市場の成長に直結する重要なファクターです。特に個人投資家にとっては、「どれだけ自由に取引できるか」「どれくらい税金がかかるか」が、参入ハードルを大きく左右します。
ここでは、主要国の税制と規制を簡単に比較し、それぞれの特徴を見ていきましょう。
| 国名 | 暗号資産の税制 | 規制状況 | 特徴・コメント |
|---|---|---|---|
| 日本 | 総合課税(雑所得)/最大55% | 金融庁による厳格な登録制度 | 税率の高さが大きなハードル/透明性は高い |
| アメリカ | キャピタルゲイン課税(15〜37%) | SECによる規制強化中 | 税率は所得水準に応じて変動/訴訟も多い |
| シンガポール | 個人は非課税(キャピタルゲイン課税なし) | MASの認可制、比較的自由 | アジアの暗号資産ハブ/企業誘致が活発 |
| ドイツ | 1年以上保有で非課税 | 金融監督庁(BaFin)が監督 | 長期保有にインセンティブ/制度明確 |
| ポルトガル | 基本的に非課税(2023年以降変更傾向) | 比較的自由な環境 | 欧州での“暗号資産天国”として有名 |
規制は信頼性を高めるが、過剰だと普及を阻害する
税制や規制は、市場の信頼性を高めるためには必要不可欠です。しかし、過度に厳格であると、新規参入が減り、イノベーションが停滞するリスクもあります。
特に日本のように税率が高く、かつ規制も厳しい国では、「個人レベルの投資が育ちにくい構造」が出来上がってしまっていることが問題です。
海外では税制がイノベーションを後押し
シンガポールやドイツのように、非課税や長期保有優遇がある国では、スタートアップや若年投資家の活動が活発です。税制の工夫が、Web3やDeFiといった次世代サービスの成長を支えています。
参考:OECD「Crypto Tax Guidelines」、国税庁・金融庁、IRS(米国)、MAS(シンガポール金融管理局)、BaFin(ドイツ)
6. 今後、暗号資産が伸びる注目の国とエリアとは?
2025年現在、暗号資産はすでに世界中で一定の普及を見せていますが、今後さらに急成長する可能性が高い国・地域もいくつか存在します。これらの国では、経済・インフラ・人口構成などの条件が整いつつあり、投資家や企業にとって新たなフロンティアとなるでしょう。
① フィリピン:Web3×ゲーム大国への変貌
フィリピンは「Axie Infinity」などのP2E(Play to Earn)ゲームで世界的に知られる国のひとつです。若年層が多く、スマホ普及率も高いため、暗号資産が報酬として機能する構造がすでに社会に根づいています。
政府も暗号資産に対して柔軟な姿勢を見せており、今後はゲーム×金融=GameFiの拠点として期待されています。
② インドネシア:人口ボーナスと規制緩和の期待
世界第4位の人口を誇るインドネシアでは、若者を中心に暗号資産への関心が急上昇しています。インフレの影響とルピアの不安定さを背景に、USDT(ステーブルコイン)などの利用も拡大中。
また、2023年に暗号資産の監督機関が金融庁から商品先物庁(Bappebti)へ移行され、柔軟な制度設計に向けた動きも進んでいます。
③ ケニア:モバイル送金文化とDeFiの融合
ケニアは「M-Pesa」などモバイルマネーが早くから定着した国として有名ですが、近年ではDeFi(分散型金融)を活用したマイクロファイナンスや小口投資が急成長しています。
銀行口座を持たないアンバンクド層が多いことから、暗号資産による金融包摂(ファイナンシャル・インクルージョン)が実現しやすい土壌があります。
④ ブラジル:政府と企業の積極姿勢が加速中
中南米最大の経済圏であるブラジルでは、2022年に暗号資産法(Marco Legal das Criptomoedas)が施行され、取引所やウォレット事業者に対する明確なルールが整備されました。
国民の約3割が何らかの形で暗号資産を保有しており、新しい金融サービスの受け入れ土壌が十分にあります。
⑤ ナイジェリア:CBDCと民間通貨の共存実験
ナイジェリアは中央銀行発行デジタル通貨(CBDC)である「eNaira」を導入した先進国のひとつですが、民間発行の暗号資産も依然として非常に活発に利用されています。
インフレや送金コストの問題を背景に、国家主導と個人ニーズの両方から成長が期待されます。
これらの国々に共通するのは、人口構成の若さ・スマホインフラの発展・政府の柔軟な姿勢です。これらが揃っているエリアは、今後Web3や暗号資産エコシステムの成長を牽引していく可能性があります。
参考:World Bank「Global Financial Inclusion Data」、Chainalysis「Crypto Adoption Index 2024」、各国金融庁公式サイト
7. 初心者が知っておくべき暗号資産投資のリスクと守るべきポイント
暗号資産の可能性に注目が集まる一方で、投資にはさまざまなリスクが伴います。特に初心者にとっては、利益だけでなくリスクの管理も重要です。ここでは、最低限知っておきたい注意点とその対策を紹介します。
① 相場のボラティリティ(価格変動)が極めて高い
暗号資産は株式や為替に比べて価格の変動が非常に激しいのが特徴です。数時間で10%以上の値動きが起こることも珍しくなく、短期的な売買では損失を出すリスクも高くなります。
対策:中長期での分散投資を意識し、一度に大きな額を投入しないこと。
② 詐欺やフィッシング被害が横行している
SNSやメールを通じた偽のエアドロップ、偽ウォレットサイト、投資勧誘など、詐欺の手口は年々巧妙化しています。
対策:公式サイトからのみウォレットや取引所を利用する/2段階認証を必ず設定する。
③ ウォレットの紛失・秘密鍵の管理ミス
暗号資産の本質は「自己管理資産」であり、秘密鍵(シードフレーズ)を紛失すれば資産は完全に失われます。取引所に預けた場合でも、ハッキングや倒産リスクはゼロではありません。
対策:ハードウェアウォレットや信頼性の高いソフトウェアを使い、秘密鍵は紙やオフラインで安全に保管する。
④ 規制変更の影響を受けやすい
国によっては、突然の法律改正により取引所の閉鎖や一部通貨の取扱停止が発生することもあります。特に新興国では、政策が流動的です。
対策:ニュースや規制の動向を日常的にチェックし、複数の手段で資産を分散する。
⑤ 税金への理解不足がトラブルに繋がる
日本では暗号資産の利益は確定申告の対象となりますが、申告漏れや間違いが多発しています。特に複数の取引所や通貨を使っていると、計算が煩雑になります。
対策:暗号資産専用の損益計算ツール(例:Gtax、クリプタクトなど)を活用する。
補足:よくある「うまい話」に注意!
「必ず儲かる」「年利20%保証」といった文句には絶対に注意してください。こうした案件の多くはポンジスキームや出口詐欺(ラグプル)である可能性があります。
暗号資産は正しく使えば大きな可能性を秘めたツールですが、リスクの把握と慎重な管理がなければ簡単に資産を失ってしまうことも。基本的なセキュリティ意識と情報収集を怠らないようにしましょう。
参考:金融庁「暗号資産に関する注意喚起」、NISC(内閣サイバーセキュリティセンター)、Crypto Crime Report(Chainalysis)
8. まとめ|日本でも今から始められるチャンスと戦略とは?
2025年現在、世界ではナイジェリアやタイ、トルコといった国々が暗号資産の普及を牽引しています。一方、日本は制度的なハードルや慎重な国民性により、まだ普及率が低い段階にあります。
しかし、それは「伸びしろが大きい」というポジティブな可能性を意味するとも言えます。
今、日本で始めるメリットは?
- すでに金融庁の規制下で信頼できる取引所が整備されている
- 大手企業(楽天、GMO、三菱UFJなど)がWeb3領域に参入
- NFTやGameFiなどのエンタメ分野からの導入も可能
- 税制改正や法整備の議論が進行中で将来的な改善が見込める
これから始める人の戦略3ステップ
- 1. 少額から始める:まずは数千円から、リスクのない範囲で購入・保有を体験。
- 2. 情報源を選ぶ:公式発表や信頼あるメディアを中心に学び、SNS情報を鵜呑みにしない。
- 3. 自分の関心分野とリンクさせる:NFTアートやWeb3ゲーム、DAOなど、興味のあるユースケースから関わる。
信頼できる国内サービス(一例)
- コインチェック(Coincheck):初心者向けUIとNFTマーケット連携
- ビットフライヤー(bitFlyer):金融庁登録済、セキュリティが堅牢
- GMOコイン:取引手数料が安く、API取引にも対応
いまはまだ、周囲の人が暗号資産を持っていないからこそ、「先行者利益」を得るチャンスがあります。全財産を投資する必要はありません。まずは一歩、小さく踏み出すことで、未来の金融やWeb3の波に自然と乗れるようになります。
暗号資産は、技術と経済の融合によって生まれた新しい資産のかたち。今後の世界経済の流れを読み解くうえでも、関心を持ち、正しい知識を得ることが何より重要です。
未来の資産形成は、「知っている人」と「知らない人」で差がつく時代へ。 まずは、知ることから始めましょう。
補足:取引金額が大きい国ランキング|実需とは異なる“投資市場の力”
前章までで解説したのは、主に「普及率」=どれだけ多くの人が暗号資産を保有しているかという観点でした。
しかし、もうひとつ重要な視点として「**取引金額(ボリューム)**」があります。これは、その国でどれだけ多くの資金が暗号資産市場で動いているかを示す指標で、主に以下のような要因が反映されます:
- 機関投資家の参入の多さ
- 国内取引所の規模
- ヘッジファンドやETFなどの影響
この取引金額ランキングで上位にくるのは、次のような国々です:
| 順位 | 国名 | 特徴 |
|---|---|---|
| 1位 | アメリカ | 機関投資家が主導/ビットコインETFなどの上場で市場拡大 |
| 2位 | 中国(香港経由) | 本土では取引禁止だが、香港・OTC市場が活発 |
| 3位 | イギリス | ロンドンを拠点としたファンド・証券会社の動き |
| 4位 | 日本 | 国内の現物・レバレッジ取引は世界的に高水準 |
| 5位 | 韓国 | 国内取引所の取引高は常に上位、アルトコイン人気 |
このように、普及率が低くても、大口取引や金融商品の影響で取引量が多い国が存在します。
普及率と取引量はそれぞれ別の視点から市場を分析するために重要で、両方を理解することで、暗号資産の全体像がよりクリアになります。
参考:Chainalysis「Crypto Adoption Index」、CoinMarketCap取引量ランキング、Binance Research 2024
本記事では、2025年時点における暗号資産(仮想通貨)の国別普及率を中心に、世界の動向と日本の立ち位置を詳しく解説しました。まず、ナイジェリアやタイ、トルコなどの国が高い普及率を誇る一方で、日本は6~8%と低水準にとどまっており、税制や規制がその要因であることが明らかになりました。
また、普及が進む国には共通して「インフレへの対応」「銀行口座を持たない層の多さ」「若年層のデジタルリテラシーの高さ」といった特徴が見られ、これらが暗号資産を生活に取り入れる強い動機となっています。
一方で、暗号資産の世界では「普及率」だけでなく、「取引金額」も重要な指標です。米国・中国(香港)・英国などは、普及率は中程度でも取引金額では世界トップクラス。これは、機関投資家や大規模ファンドによる資金流入が活発であることを意味します。
初心者向けには、リスク管理や詐欺対策、税制対応を含めた注意点も紹介。日本においても、GMOや楽天など大手企業がWeb3市場に進出し始めており、今後の展望は明るいものがあります。
暗号資産投資は、単なる流行ではなく、金融の新しい形です。普及率や制度、リスクを正しく理解することで、より賢く未来の資産形成に備えることができます。

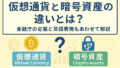
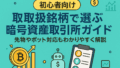
コメント