- 北米・欧州・アジアの注目Web3企業15社を紹介
- 海外Web3サービスを使う際の注意点を具体的に解説
- 日本人が世界のWeb3に触れるための第一歩がわかる
- 世界の注目Web3企業15社を地域別に紹介(北米・欧州・アジア)
- 各企業の特徴と代表トークン/サービスを解説
- 海外Web3プロジェクトを使うときの注意点
2025年現在、世界中でWeb3関連のスタートアップやサービスが急速に進化しています。
本記事では、北米・欧州・アジアから注目のWeb3企業を各5社ずつ、計15社を日本人向けにわかりやすく解説します。
北米の注目Web3企業5選
アメリカを中心とした北米地域では、Web3の開発・投資・普及が世界をリードしています。
ブロックチェーンの基盤技術からDeFi、NFTマーケット、DAO支援まで、多様なプロジェクトが日々進化を遂げています。
ここでは、特に注目される北米発のWeb3企業を5社厳選し、それぞれの特徴や取り組みを紹介します。
① Coinbase(アメリカ)
ナスダック上場の暗号資産取引所であり、DeFi・NFTにも積極展開。
Coinbase WalletやBaseチェーンなど、エコシステムを独自に拡張中。
初心者にも使いやすく、規制遵守に強みがあります。
② OpenSea(アメリカ)
NFTマーケットプレイスの代表格。アートからゲームまで幅広いNFTを取り扱い。
誰でもNFTを作成・販売できるUIのわかりやすさが人気の理由です。
日本人クリエイターの利用も増加しています。
③ ConsenSys(アメリカ)
Ethereum開発の中心企業。MetaMaskなどの主要ツールを開発。
Web3の基盤を支える存在として、多くのプロジェクトと連携。
MetaMask Institutionalなど、法人向けサービスも拡充中です。
④ Dapper Labs(カナダ)
「NBA Top Shot」や「CryptoKitties」などNFTの火付け役。
独自ブロックチェーンのFlowを開発し、ゲーム・IP活用に特化。
日本のアニメ・スポーツIPとも連携の可能性あり。
⑤ Chainalysis(アメリカ)
ブロックチェーン分析のリーディング企業。
マネーロンダリング対策やハッキング追跡で政府や企業と提携。
安全性と信頼性の可視化に不可欠な存在です。
欧州の注目Web3企業5選
欧州では、法整備や公共インフラとの連携を重視したWeb3プロジェクトが数多く存在します。
特にEU圏内では、デジタルID、CBDC、Web3教育などに関する官民連携が進んでおり、社会実装に近い形での実験が行われています。
ここでは、2025年現在注目される欧州発のWeb3企業5社を紹介します。
① Ledger(フランス)
世界トップクラスのハードウェアウォレットメーカー。
Ledger Nanoシリーズは個人投資家から機関投資家まで幅広く支持されています。
セキュリティとユーザー体験のバランスに定評があります。
② Sorare(フランス)
サッカーを中心にしたファンタジーNFTゲームを展開。
UEFAやJリーグと提携し、実在選手を使ったゲーム体験が人気。
スポーツ×NFTの先駆けとして注目されています。
③ Gnosis(ドイツ)
Ethereum上でのマルチシグウォレットや予測市場プラットフォームを提供。
Gnosis SafeはDAOやDeFi運用に欠かせないインフラです。
分散型組織の支援にも積極的です。
④ Boson Protocol(イギリス)
Web3とeコマースの融合を目指すプロジェクト。
スマートコントラクトを使って「デジタルからリアル商品へ」自動決済を実現。
Web3時代のショッピング体験を再定義しています。
⑤ DappRadar(リトアニア)
世界最大級のDapps(分散型アプリ)分析プラットフォーム。
利用者数、取引量、チェーンごとのトレンドを可視化。
投資家・開発者双方に役立つデータを提供しています。
アジアの注目Web3企業5選
アジアでは、日本・中国・シンガポール・韓国などを中心に、独自の視点からWeb3を推進する企業が増加しています。
地域特性を活かしながら、取引所、NFT、メタバース、DAO、教育など幅広い分野での活躍が見られます。
ここでは、注目すべきアジア発のWeb3企業5社をご紹介します。
① KuCoin(セーシェル/運営本部は中国系)
世界200以上の国と地域で展開するグローバル取引所。
多様なトークンの取扱いとIEOプラットフォーム(KuCoin Spotlight)で人気を集めています。
日本語対応もあり、国内ユーザーの利用も増えています。ちなみに筆者も愛用しています
② MEXC Global(シンガポール起源のグローバル企業)
2018年に設立された暗号資産取引所。
世界170か国以上で展開し、先物・ローンチパッド・レバレッジトークンなど幅広い商品に対応しています。
日本語にも対応しており、日本人ユーザーにも人気。通称、抹茶(まっちゃ)と呼ばれているそうです
手数料の割引やキャンペーンも豊富で、初心者〜中上級者に対応。ちなみに筆者も愛用しています
③ Animoca Brands(香港)
ブロックチェーンゲームとNFTの投資会社・開発会社。
「The Sandbox」や「REVV Racing」など多数のWeb3プロジェクトに出資・連携。
日本IPとの連携やWeb3教育への支援も積極的です。
④ ZEPETO(韓国・NAVER Z)
アバター×メタバースの先駆けとして、特にZ世代に人気。
K-POPやアジアの芸能・ファッションカルチャーと連携し、NFT導入も進行中。
世界で3億人以上のユーザーを抱える巨大プラットフォームです。
⑤ Coin98(ベトナム)
マルチチェーン対応のWeb3ウォレット・DeFiプラットフォーム。
SolanaやEthereumを始め多くのチェーンに対応。
東南アジア圏を中心に、草の根的な普及を進めています。
Web3を始めるには?海外サービス利用時の注意点
世界のWeb3プロジェクトに魅力を感じて、「自分も使ってみたい!」と思った方も多いでしょう。
しかし、日本から海外のWeb3サービスや取引所を利用する際には、いくつかの重要な注意点があります。
安全に利用するためにも、事前に知っておくべきポイントを整理しておきましょう。
① 日本語対応・サポート体制の確認
英語圏のサービスが多いWeb3ですが、日本語対応の有無は利用体験を大きく左右します。
UIが日本語で使いやすいか、困ったときに日本語サポートが受けられるかを確認しましょう。
KuCoinやMEXC、Bybitなどは、日本語ページやFAQが充実しています。
② 日本からの利用が「制限対象」ではないか
一部の海外取引所は、日本の金融庁との規制対応のため、日本居住者による利用を制限している場合があります。
例:Binanceは一部機能が日本からのアクセスでは使用不可。
VPNなどを使ったアクセスは規約違反となる可能性があるため、事前に利用可否を確認してください。
③ 送金・出金・ガス代などの費用も要チェック
海外のWeb3サービスを使うには、日本の取引所から暗号資産を送金する必要があります。
送金手数料、最低入金額、ガス代などはサービスによって異なります。
少額から始めたい人は、手数料が少ないブロックチェーン(Polygon、Solanaなど)を活用するのも一つの手です。
④ フィッシング詐欺・偽サイトへの警戒
人気サービスになりすました偽サイトや、公式を装ったX(旧Twitter)アカウントも存在します。
必ず公式サイトのURLをブックマークし、安易にウォレット接続や署名をしないよう注意しましょう。
⑤ ウォレット連携と秘密鍵の管理
海外の多くのWeb3サービスでは、MetaMaskやPhantomなどのウォレット接続が必要です。
自己管理のウォレットは利便性が高い反面、秘密鍵・リカバリーフレーズの紛失が資産消失につながります。
初心者は最初に少額でテストしながら、慎重に操作することをおすすめします。
まとめ|世界のWeb3を知り、日本からも一歩を踏み出そう
Web3の波は、もはや一部の国や企業にとどまらず、世界中で次世代のインターネット体験を変えようとしています。
北米ではブロックチェーンインフラやNFT文化が進化し、欧州では持続可能性や分散型ガバナンスが進み、アジアではスピード感ある取引所や独自のゲーム文化が花開いています。
この記事で紹介した15社は、その中でも特に注目度が高く、日本人ユーザーにとっても使いやすい・親しみやすい特徴を持つプロジェクトばかりです。
もちろん、海外サービスを使う際には、言語・規制・セキュリティなどの注意点もあります。
でも、しっかりと調べて正しい手順を踏めば、日本にいながら世界の最先端のWeb3に触れることは十分に可能です。
大切なのは、「まずは小さく始めてみること」。
MetaMaskのインストールや、信頼できる日本の取引所での暗号資産の準備からスタートして、自分に合ったWeb3体験を見つけてください。
世界の技術が手元に届くこの時代。次にその未来をつくるのは、あなたかもしれません。
- 北米・欧州・アジアのWeb3企業を各5社ずつ紹介
- NFT、DeFi、メタバース、インフラなど分野別に分類
- CoinbaseやAnimocaなどグローバルに活躍する企業を解説
- MEXCはシンガポール起源のグローバル取引所として紹介
- 海外サービスを使う際のリスクと対策を丁寧に解説
- 日本語対応の有無や規制制限に注意が必要
- MetaMaskや取引所口座の準備がWeb3の第一歩
- 世界のWeb3動向を知ることで視野が広がる
- 海外プロジェクトでも日本から体験・参加が可能

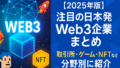

コメント