仮想通貨と暗号資産、なにが違うの?
最近ニュースやSNSでよく見かける「暗号資産」という言葉。
でも、ちょっと前までは「仮想通貨」と言われていた気がしませんか?
この2つ、実は同じように見えて意味や使い方に違いがあるんです。
この記事では初心者の方でもわかるように、仮想通貨と暗号資産の違いをやさしく解説します。
ニュースで見かける表現の意味や、今後どちらの言葉を使えばいいかも理解できるようになりますよ。
正しい知識を持つことは、安全な資産管理や投資判断にもつながります。
まずは、「なんとなく知ってるつもり」から一歩踏み込んで、正確な意味を押さえておきましょう。
そもそも「仮想通貨(かそうつうか)」という言葉が登場したのは、ビットコインなどのデジタルマネーが話題になり始めた2010年代前半のことです。
当時は「インターネット上の通貨」「国が発行しない通貨」として扱われ、革新的な金融技術として注目されていました。
一方で、「暗号資産(あんごうしさん)」という言葉が使われるようになったのは、2019年ごろから。
これは日本の法律(資金決済法)の改正によって公式に定義された呼び名です。
つまり、「仮想通貨」は俗称であり、「暗号資産」は法的な正式名称という違いがあります。
この違いを知っておくと、ニュース記事や金融庁の発表を見たときにも内容を正しく理解できるようになります。
次の見出しでは、「仮想通貨」と「暗号資産」のどちらが今主流なのかを具体的に見ていきましょう。
「仮想通貨」は古い言い方?今は「暗号資産」が主流?
「仮想通貨」と聞いてピンとくる人は多いと思いますが、最近では「暗号資産」という言葉を目にする機会が増えてきました。
では、いったいどちらが現在の正式な呼び方なのでしょうか?
結論から言えば、現在の法律上の正式名称は「暗号資産」です。
これは2019年5月に公布された改正資金決済法によって、「仮想通貨」という表記から「暗号資産」へと統一されたためです。
つまり、ニュースや行政文書、証券会社・取引所などが使う場面では、「暗号資産」が標準的な表記となっています。
一方で、「仮想通貨」という言葉もまだ日常的には多く使われており、完全になくなったわけではありません。
たとえば、検索エンジンでの月間検索回数を比較してみると、「仮想通貨」の方が依然として数倍多く検索されています。
これは一般の人々にとって「仮想通貨」の方が浸透しており、聞き慣れているためと考えられます。
実際、ビットコインやイーサリアムなどの説明をする際にも、「仮想通貨」という用語を使った方が初心者には伝わりやすいことが多いのです。
しかし、法的な観点や正確な情報提供の必要がある場面では、「暗号資産」を用いるのが適切です。
このように、状況に応じて言葉を使い分けることが、現代では求められていると言えるでしょう。
次の章では、「暗号資産」がどう定義されているのか、金融庁の公式な説明を見ていきます。
金融庁が定める「暗号資産」の定義とは?
「暗号資産」という言葉は、ただの言い換えではなく法律で明確に定義された正式な用語です。
この定義は金融庁と日本の資金決済法に基づいています。
具体的には、暗号資産とは以下のように定義されています。
「不特定の者に対して、代価の弁済に使用できることができ、かつ法定通貨(日本円など)と交換できる、電子的に記録された財産的価値」
さらに、電子的に移転可能であり、法定通貨または資産と交換できるものが暗号資産として認められます。
ここでのポイントは、「法定通貨ではない」かつ「財産的価値がある」ということです。
つまり、ビットコインやイーサリアムのように価値のやり取りができる仕組みを持ったデジタル資産が暗号資産なのです。
これに対して、「電子マネー(SuicaやPayPayなど)」や「ポイント」は暗号資産には該当しません。
なぜならそれらは法定通貨を基準として企業が発行する決済手段だからです。
この定義は法的な枠組みや金融規制の対象を明確にするためにも非常に重要です。
たとえば、暗号資産を扱う取引所は「暗号資産交換業者」として金融庁の登録を受ける必要があります。
つまり、「暗号資産」という言葉には、法律に裏付けされた信頼性と規制の対象であることが含まれているのです。
この背景を理解しておくことで、投資判断やサービス選びにも役立つ視点を持つことができます。
次は、この用語がなぜ導入されたのか、背景に迫っていきましょう。
なぜ言い方が変わったの?「仮想通貨」から「暗号資産」への背景
「仮想通貨」から「暗号資産」へ。
言葉の変化の裏には、日本政府と金融庁による明確な意図と方針があります。
単なる呼び名の違いではなく、投資家保護やマネーロンダリング防止など、法整備の一環として導入されたのです。
もともと「仮想通貨」という言葉は、2017年の資金決済法改正時に用いられていました。
しかし、「通貨」という表現が、日本円やドルなどの法定通貨と混同される恐れがあるとして、金融庁が懸念を示していました。
そこで2019年の法改正で、「仮想通貨」は正式に「暗号資産」という法的名称に置き換えられたのです。
この変更により、一般消費者が「国家が価値を保証している通貨」と誤解するリスクが低くなりました。
加えて、国際的な金融規制の動向もこの用語変更に影響を与えています。
たとえば、FATF(金融活動作業部会)などの国際組織は「Virtual Asset(バーチャルアセット)」という表現を推奨しており、これを日本では「暗号資産」と訳しています。
つまり、「暗号資産」への移行は、国内だけでなく国際的な法制度との整合性を図るという意味も持っていたのです。
この用語変更は、一時的な流行語ではなく、制度として根付くための重要な一歩でした。
このようにして、「仮想通貨」から「暗号資産」へと表現が変わった背景には、投資家保護と制度的な信頼性を確保する目的があるのです。
次は、実際にどのように使われているのか、ニュースや取引所などの事例をもとに見ていきましょう。
実際にはどう使われてる?ニュース・取引所・SNSでの使われ方
「暗号資産」が法律上の正式名称であることは分かったけれど、
では私たちが日常的に目にするニュースやSNSでは、実際どちらの言葉が使われているのでしょうか?
実は、使い方には場面ごとの傾向があります。
法的・公式な文脈では「暗号資産」、日常会話やマーケティングでは「仮想通貨」が依然として使われています。
たとえば、NHKや日経新聞などのニュースメディアでは、「暗号資産」が一般的です。
これは正確性を重視した用語選択で、法律や制度と整合性を取るためです。
一方、YouTubeやX(旧Twitter)などのSNSや個人ブログでは、今でも「仮想通貨」という表現が主流です。
さらに、国内取引所の公式サイトを見てみると、
・bitFlyer → 「暗号資産」
・Coincheck →「仮想通貨(暗号資産)」のように併記
・GMOコイン →「暗号資産」
というように、公式には「暗号資産」を用いつつ、ユーザーの認知度に配慮して「仮想通貨」も使われているケースが目立ちます。
つまり、場面に応じて柔軟に使い分けているのが実情なのです。
これは、いかに「仮想通貨」という言葉が人々の中に深く根付いているかを示しています。
また、Google検索やYouTubeなどの検索ワードとしては、現在も「仮想通貨」の方が圧倒的に多く検索されているのが現状です。
そのため、初心者向けコンテンツやライトユーザー向けの情報発信では、「仮想通貨」が効果的に使われることもあります。
次の章では、「自分はどちらを使えばいいのか?」という疑問にお答えします。
使い分けのヒントを、シーン別に紹介していきましょう。初心者はどちらを使えばいい?シーン別の使い分け方
「仮想通貨」と「暗号資産」の違いはわかったけど、
結局どっちを使えばいいの?と迷う方も多いのではないでしょうか。
実はこの問題、使う場面や相手によって適切な言葉が変わってくるんです。
ここでは、初心者がシーン別にどちらを使えば良いか、わかりやすく整理してみましょう。
- 友人や家族との会話:「仮想通貨」がおすすめ。聞き慣れていて伝わりやすいから。
- ブログ・SNS投稿:検索されやすく親しみのある「仮想通貨」、ただし情報の正確性が必要な時は「暗号資産」に切り替えても◎
- 金融・法的な文脈(契約・説明書など):「暗号資産」を使用。正確で信頼される表現。
- 投資アプリ・取引所の登録や操作時:取引所の用語に合わせて「暗号資産」が基本。
このように、日常的には「仮想通貨」、公式や法律的には「暗号資産」というのが基本的な考え方です。
どちらが間違いというわけではありませんが、使う言葉で信頼性や理解度が変わることもあるため、意識して使い分けるのがベストです。
日本の金融庁では、「暗号資産」を英語で “Crypto-assets” または “Crypto-assets under the Payment Services Act” と表記しています。
この表記は、2019年の資金決済法改正時に採用され、英訳文書や国際会議でも使われています。
FATF(金融活動作業部会)などの国際基準機関も「Crypto-assets」を用いており、これがグローバルスタンダードです。
「仮想通貨」は以前は英語で “Virtual Currency” と呼ばれていました。
これは初期のビットコイン登場時によく使われていた表現ですが、現在ではより包括的で正確な「Crypto-assets」に置き換えられつつあります。
まとめ:どちらの言葉も正解。でも違いを知っておこう
ここまで「仮想通貨」と「暗号資産」の違いや使い分けについて解説してきました。
どちらの言葉も意味としては同じ資産を指していますが、使われる場面や背景には大きな違いがあります。
日常会話やSNSでは「仮想通貨」という言葉が依然として広く使われていますし、初心者にとっても親しみやすい言葉です。
一方、法律や制度の文脈では「暗号資産」が正式名称として位置付けられており、正確な情報提供には不可欠です。
つまり、相手や目的に応じて言葉を選ぶことが、これからの時代には求められています。
投資や資産管理をより安全に行うためにも、言葉の違いを理解することは大切な一歩です。
- 「仮想通貨」と「暗号資産」の違いを解説
- 暗号資産は2019年以降の法的な正式名称
- 仮想通貨は旧称で一般には浸透中
- 金融庁による明確な定義と法律上の扱い
- 用語変更の背景には誤解防止と国際整合性
- 実際の取引所・メディアでは併用される傾向
- 「Crypto-assets」が国際的な英語表現
- 初心者には仮想通貨、公式には暗号資産が適切
- 状況に応じた言葉の使い分けが重要

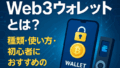
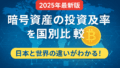
コメント